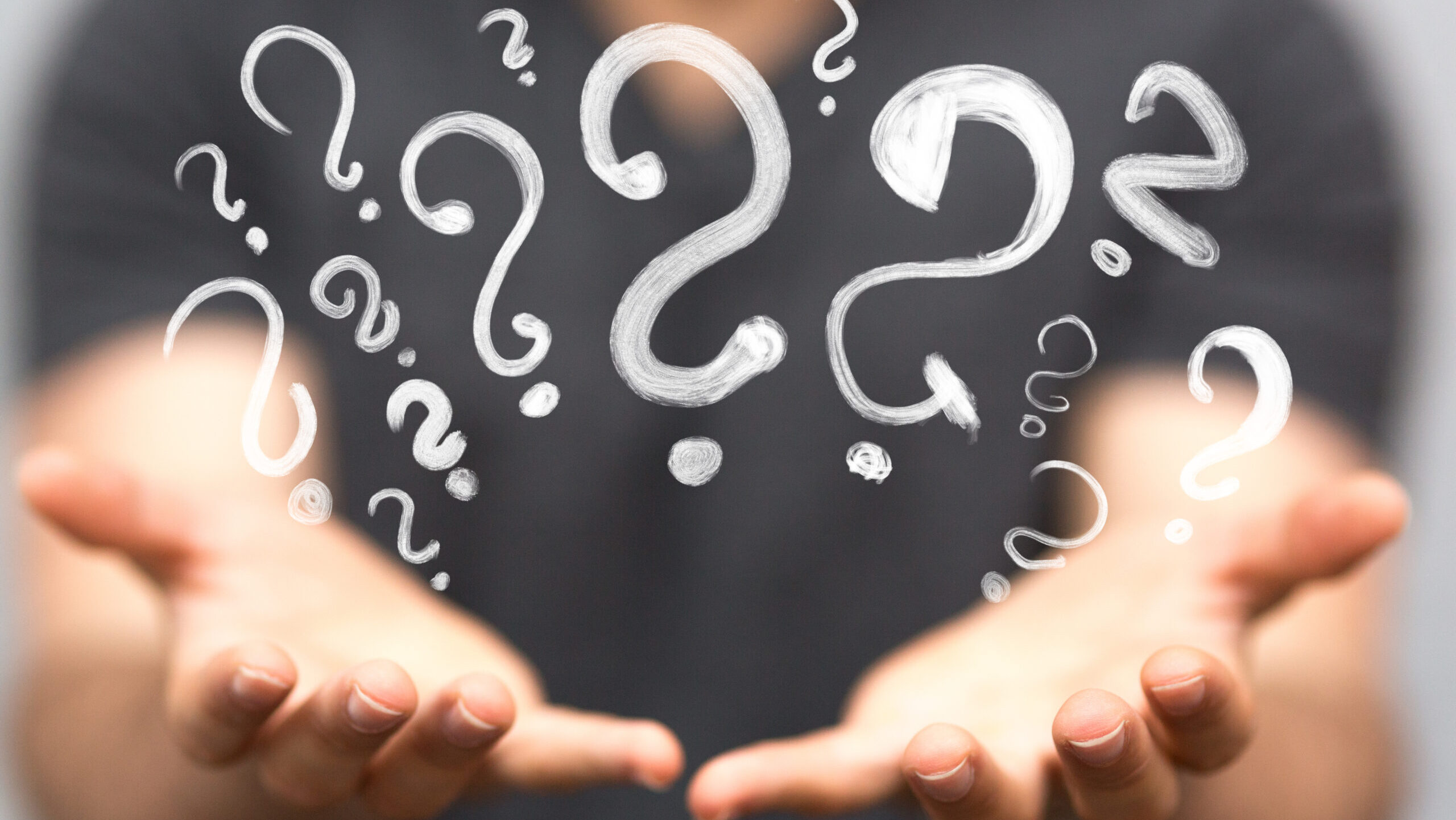キャリアアップ助成金は、中小企業の人材確保や社員定着を支援する制度で、多くの企業から注目されています。しかし、「手続きが難しそう」「審査が厳しくて申請しても通らなかった」といった声も少なくありません。
今回は、近年ますます厳しくなっているキャリアアップ助成金の審査について、なぜ厳しくなっているのか、どんな点に注意すべきかをわかりやすく解説します。不支給にならないためのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
助成金・補助金の「無料相談」を実施中!
累計6,000社以上を支援した実績豊富な助成金・補助金の専門チームが、
貴社のご相談に丁寧に対応いたします。
「使える助成金があるか知りたい!」「どんな補助金があるのか相談したい!」等
お気軽にご相談ください。
キャリアアップ助成金とは?初心者向けにわかりやすく解説
まず、キャリアアップ助成金の概要を簡単に見ていきましょう。
キャリアアップ助成金の目的と仕組み
キャリアアップ助成金は、非正規雇用の方を正社員に登用したり、処遇改善を行ったりする企業を支援する制度です。厚生労働省が設けており、企業が従業員のキャリアアップに取り組むことで、企業の成長と従業員の定着を後押しする仕組みになっています。
制度には、非正規雇用労働者から正規雇用への転換、賃金規定の改定、賞与や退職金制度の導入などによる処遇改善など、7つのコースがあります。各コースに定められた要件を満たすことで、助成金を受給できます。
中小企業が活用するメリット
中小企業にとっては、人材の定着や人件費の補助につながる大きなメリットがあります。採用コストが高まっている今、限られた人材を確保・育成するために、この制度を積極的に活用する企業は増えています。
キャリアアップ助成金の審査が厳しいと言われる理由
結論から言えば、キャリアアップ助成金の審査は年々厳しくなっています。その背景には、不正受給の増加が大きく関わっています。
不正受給の増加と国のチェック強化
近年、助成金制度を悪用した不正受給が目立っています。
たとえば、雇用調整助成金等の不正受給件数は、2020年4月から2025年2月28日までに1,620件に達しており、2024年の1年間だけでも625件も不正受給が確認されています。また、キャリアアップ助成金においては、例年約7万件近く活用されている一方で、約200件の不正受給が発覚しています。
この状況を受け、厚生労働省は審査体制を強化し、チェックの目がより厳しくなっています。 さらに、不正受給を行った事業主には返還命令だけでなく、実名の公表といった厳しい処分が下されることもあり、不正に対する監視が年々強化されています。
形式的な申請では通らない現状
以前は「必要書類をそろえれば通る」と思われていたケースもありましたが、今はそうはいきません。書類の整合性や実態確認が徹底されており、少しでも矛盾があれば追加書類の提出や実地調査を求められることもあります。
その結果、不支給となってしまうケースも珍しくなく、形式的な申請では受給が難しいのが現状です。
(参照)
- 株式会社東京商工リサーチ 「「雇用調整助成金」の不正受給公表 1,620件 公表企業の倒産は92件、倒産発生率は5.6%」(2025/3/21) 「雇用調整助成金」の不正受給公表 1,620件 公表企業の倒産は92件、倒産発生率は5.6% | TSRデータインサイト | 東京商工リサーチ
- 厚生労働省HP 「キャリアアップ助成金」―不正受給について― キャリアアップ助成金|厚生労働省
- 厚生労働省HP 「キャリアアップ助成金」不正受給に関するリーフレット 001450307.pdf
キャリアアップ助成金の申請で注意すべきポイント5つ
厳格化する審査をクリアし、確実に助成金を受給するためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。ここでは、特に重要な5つのポイントをご紹介します。
ポイント1:就業規則・賃金規定や雇用契約書の整合性
キャリアアップ助成金を申請する際には、就業規則や賃金規定がコースごとの要件を満たしているかどうかが厳しく審査されます。申請内容と、実際の就業規則や雇用契約書の内容が一致していることが大前提です。矛盾があると審査に通りません。
ポイント2:出勤簿・賃金台帳など労務管理記録の整備
助成金を申請する際、出勤簿またはタイムカード、賃金台帳など、労務関連書類の提出が必須となります。労務管理記録が正しく整備されているか確認が必要です。これらの書類に不備や虚偽の内容があると、不正受給とみなされるリスクがあります。
厚生労働省が示す留意事項
厚生労働省が発行している『不正受給防止のための留意事項について』には、次のような注意点が明記されています。
- 提出書類の差し替えや訂正は不可:一度提出した書類は、原則として差し替えや訂正が認められません。提出前に内容を慎重に確認する必要があります。
- 原本等の提出が必須:出勤簿や賃金台帳などの添付書類は、法定帳簿として事業場で調製された原本、または複写機で複写したもの(原本等)でなければなりません。転記や加工を施した書類では、不支給となります。
- 審査への協力義務:申請内容に疑義がある場合、労働局から追加書類や補正を求められることがあります。指定期日までに対応しなければ、不支給決定となります。
これらの点を踏まえると、申請に使用する書類は「正確性」「信頼性」「完全性」が求められることがわかります。
ポイント3:キャリアアップ計画書の事前提出と助成対象期間の厳守
キャリアアップ助成金では、キャリアアップ計画書を事前に提出し、認定を受ける必要があります。
この計画書に記載した期間内に、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を実施しなければ、助成金の対象にはなりません。申請時期を誤ると、それだけで受給資格を失う可能性があります。
ポイント4:雇用実態と申請内容の食い違いを防ぐ
「契約上は正社員になっているが、実態はアルバイト扱い」といったケースは不支給となります。書類上の内容と実際の雇用実態が一致していることが重要です。
ポイント5:社会保険加入・労働法令違反がないかチェック
未払い残業代や社会保険未加入など、労働法令違反があると助成金は受給できません。申請前に必ず、労務管理が適正に行われているかを確認しておきましょう。参考:厚生労働省HP 「キャリアアップ助成金」 キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)(パンフレット)P5 「不正受給防止のための留意事項について」 001512871.pdf
助成金申請を自社で行うのは負担が大きい
「これなら自社でできそうだ」と思われる方もいるかもしれません。しかし、助成金申請は以下のように多大な労力がかかります。
- 膨大な書類の準備:申請には、多数の書類が必要となることもあります。
- 複雑な要件の確認:各コースに細かな要件があり、最新情報の確認が欠かせません。
- 申請後の対応:労働局からの質問や追加書類の提出依頼に対応する必要があります。
- 不正受給のリスク:悪気がなくても、書類の不備や要件の誤認で不正受給と判断される場合があります。
せっかく準備しても、不備があれば不支給となり、その労力が無駄になってしまうこともあります。本業の傍らでこれらを正確にこなすのは、専門知識のない方にとって非常に大きな負担と言えるでしょう。
助成金申請は社会保険労務士への委託も一つの選択肢です
「自社での申請は不安」「本業に集中したい」という場合は、助成金に詳しい社会保険労務士(社労士)に相談するのが賢い選択です。社労士に依頼するメリットは次のとおりです。
- 最新の制度改正や要件を把握している:助成金制度は毎年のように改正があります。専門家である社労士は、最新情報や複雑な要件を熟知しているため、安心して任せられます。
- 申請書類作成から労働局とのやり取りまで代行:就業規則や雇用契約書のチェック、申請書類の作成から労働局との対応までを任せられるため、社内の負担を大きく減らせます。
- 不支給リスクを減らせる:社労士に依頼することで、書類の整合性を確認しながら申請を進めてもらえるため、不支給になるリスクを下げられます。
- 経営者や人事担当者は本業に集中できる:助成金申請に追われることなく、採用や社員育成といった本業に専念できます。
助成金・補助金の「無料相談」を実施中!
累計6,000社以上を支援した実績豊富な助成金・補助金の専門チームが、
貴社のご相談に丁寧に対応いたします。
「使える助成金があるか知りたい!」「どんな補助金があるのか相談したい!」等
お気軽にご相談ください。
まとめ
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の処遇改善を図り、企業価値を高めるための有効なツールです。しかし、不正受給の増加により、キャリアアップ助成金の審査は以前より厳しくなっていて、そんな厳格化する審査を乗り越えるには、専門的な知識と正確な手続きが不可欠です。
必要なポイントを押さえれば受給は可能ですが、社内だけで対応するのは大きな負担です。当SATO社会保険労務士法人では、キャリアアップ助成金をはじめとする各種助成金申請をサポートしています。安心して申請を進めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。