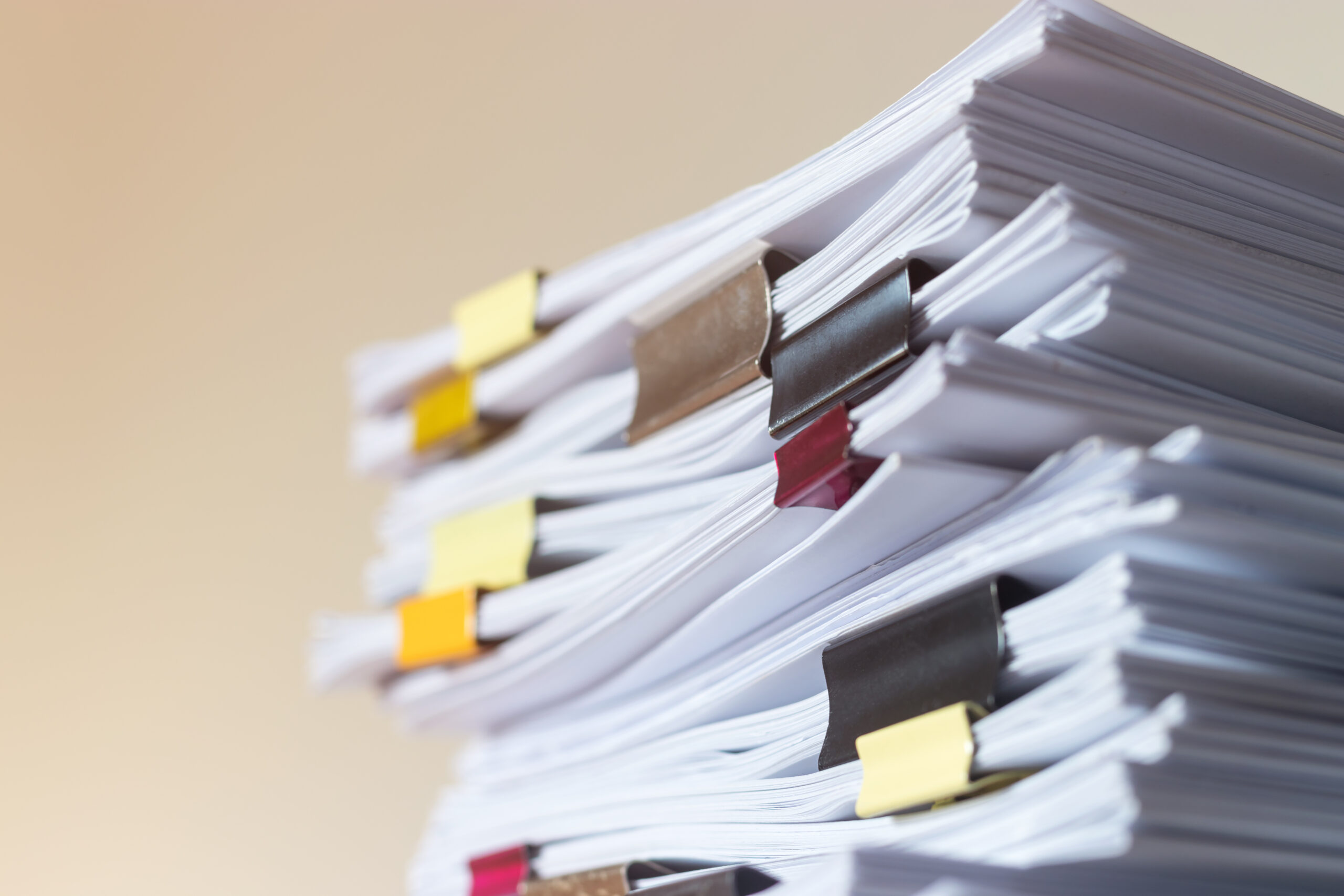企業が円滑な経営を行うためには、社内のルールを明確にすることが欠かせません。そのルールを定めたものが「就業規則」であり、それを労働基準監督署に提出する際に必要となるのが「意見書」です。本記事では、就業規則の意見書とは何か、その役割や作成方法、具体的な記載例までを丁寧に解説します。
就業規則でお困りならご相談ください!
「就業規則をまだ作っていない」「昔作ったけど何年も見直していない」
「とにかく安く就業規則を作りたい」など
ぜひSATO社会保険労務士法人の
就業規則作成サービスをご利用ください
就業規則の意見書とは
就業規則の意見書とは、企業が就業規則を作成または変更する際に、労働組合や従業員代表の意見を記載し、労働基準監督署に提出する書類です。労働者の声を反映し、企業のルールが一方的なものになることを防ぎます。
そもそも就業規則とは
就業規則とは、従業員の労働条件や、社内で守るべきルールを明文化した社内規定です。例えば、勤務時間、休日、賃金、退職に関するルールなどが含まれます。会社のルールを定めることで、労使間のトラブルを未然に防ぎ、公正な労働環境を整備することができます。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇用する事業場には、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。
意見書は就業規則の届出をする際に添付する書類
就業規則を新たに作成した場合、その就業規則を管轄の労働基準監督署へ届出しなければなりません。これは就業規則の内容が法令に沿ったものであるかどうか、労基署がチェックするためです。既に作成した就業規則の内容を変更した場合も同様に届出が必要です。
この労基署への届出をするとき、就業規則に添付するのが「意見書」です。
就業規則に意見書が必要とされる理由
就業規則は会社のルールを定めた重要な文書です。これを会社が一方的に作成・変更してしまうと、労働者にとって不利益が生じるおそれがあります。
そのため、会社が就業規則を作成または変更する際には、労働者代表に内容を確認させ、意見を述べる機会を設けることが義務づけられています。そして、この意見聴取の手続きが適正に行われたことを明らかにするため、意見書の提出が必要とされているのです。
就業規則の意見書の書き方
意見書は、法律で書式が決まっているわけではありませんが、後々のトラブルを防ぐためにも、記載すべき内容や形式を押さえておくことが大切です。
意見書の書式に指定はない
就業規則の意見書には、特定の様式は定められていません。そのため、企業ごとにオリジナルのフォーマットを作成して提出することも可能です。
ただし、一から作成するのは手間がかかるため、厚生労働省や労働局が公表している雛形を利用することをおすすめします。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu_zenkoku.html
意見書に記載する内容
意見書には、以下の項目を盛り込むのが通例です。
- 作成日付
- 宛先(会社名および代表者名)
- 意見を求められた日
- 意見の内容(異議の有無、具体的な意見)
- 労働組合の名称、又は従業員代表の役職および氏名
- 従業員代表の選出方法(労働組合がある場合は不要)
これらを記載することで、就業規則に対する意見聴取の内容が明確になり、後のトラブル防止にもつながります。
日付の違いに注意
意見書には2つの日付を記載します。
意見書の冒頭に記載する作成日付は、従業員代表が実際に意見書を作成した日付を記載します。一方、宛先の下部に記載する日付については、会社側から意見を求められた日付を記載します。
誤ってどちらも同じ日付を記載するケースが少なくありません。会社から意見を求められた日に、意見書を即日作成したというケースでない限り、この2つの日付は異なるので、混同しないよう注意が必要です。
就業規則の意見書に署名・押印は不要
2021年4月以降、行政手続きのデジタル化の一環として、就業規則の意見書においても署名・押印は不要となりました。
そのため、当事者が自筆(署名)する必要はなく、パソコンによる印字や第三者の代筆(記名)で問題ありません。
意見書の記入例
就業規則の内容に異議がない場合
意見書において、就業規則に異議がない場合は、以下のような文言を記載すれば十分です。
- 「就業規則案について異議なし」
- 「今回の改定案について特段の異議はございません」
就業規則の内容に異議がある場合
一方で、内容に異議がある場合は、具体的にどの部分に意見があるかを明記します。
- 「第10条について、始業時刻が8時となっていますが、9時に変更していただきたい」
- 「第20条について、定年が60歳とされていますが、65歳に変更を希望します」
意見書の作成手順
就業規則の意見書は以下の手順で作成するのが一般的です。
従業員代表の選出方法
労働者の過半数を組織する労働組合がない場合は、まず、労働者の中から従業員代表者を選出します。この選出は、挙手や投票など、民主的な手続きで行う必要があります。そのため、会社側が従業員代表を指名するなど、会社側の意向によって選出することはできません。
また、従業員代表であることや、従業員が代表者になろうとしていることなどを理由に、会社側が不利益な取り扱いをすることも禁じられています。
意見の内容は就業規則の効力に影響ない
会社は就業規則について、従業員代表から意見を聴取する義務がありますが、その意見に従う義務はありません。法的には、意見を聴いたという事実があれば就業規則の効力には問題ありません。
とはいえ、就業規則の内容が労働者の働き方に直接影響するものである以上、できるだけ意見を取り入れて内容を検討することが望ましいです。
意見書の提出を拒否された場合
意見書の提出を労働者側が拒否するケースも考えられます。このような場合でも、企業側が意見聴取の機会を設けたことを記録・保存していれば、就業規則の届出は可能です。
また、意見書が添付できないときは、労働基準監督署に「意見書不添付理由書」を提出しましょう。
就業規則のことならSATO社会保険労務士法人にご相談ください
就業規則は、その内容や作成手続きに法律上のルールが定められています。適切な手順を踏まずに作成した場合、せっかく整備した就業規則が無効と判断されることもあり得ます。また、法令に従うだけでなく、会社の実情や社風を反映した内容にしなければ、従業員との間でトラブルが発生するリスクもあります。
そのため、就業規則の作成は専門的な知識と実務経験が求められる作業です。自社での対応が難しいと感じたときは、専門家に相談するのも1つの手段です。
SATO社会保険労務士法人は、業界最大級の規模を誇る社労士事務所として、全国の企業を対象に、就業規則の作成から労働基準監督署への届出までをトータルでサポートしています。中小企業から大企業まで、業種や規模を問わず、各社の実情に合わせたサービスをご提供いたします。
「制度は整えたいけれど、何から始めたらいいかわからない」「過去の就業規則を見直したい」といったお悩みも、まずはお気軽にご相談ください。
就業規則でお困りならご相談ください!
「就業規則をまだ作っていない」「昔作ったけど何年も見直していない」
「とにかく安く就業規則を作りたい」など
ぜひSATO社会保険労務士法人の
就業規則作成サービスをご利用ください
まとめ
就業規則の意見書は、法令で定められた義務であると同時に、企業運営における重要な実務対応のひとつです。常時10人以上の労働者を雇用する事業場では、就業規則を作成・変更した際に、労働基準監督署への届出が必要ですが、このとき添付しなければならないのが「意見書」です。
意見書には法的な様式の指定はありませんが、記載漏れがあると受理されない可能性もあるため、労働局のテンプレートを利用することをおすすめします。近年は署名・押印も不要となり、より簡易に提出できるようになっています。
意見書の作成には、まず労働者代表の選出から始まり、意見の聴取、そして記載内容の確認と段階を踏んだ手続きが必要です。労働者代表の選出や意見聴取が適正でない場合、形式的に意見書を整えても有効と認められないことがあるため、正しい手順をしっかりと把握しておきましょう。
就業規則でお困りならご相談ください!
「就業規則をまだ作っていない」「昔作ったけど何年も見直していない」
「とにかく安く就業規則を作りたい」など
ぜひSATO社会保険労務士法人の
就業規則作成サービスをご利用ください