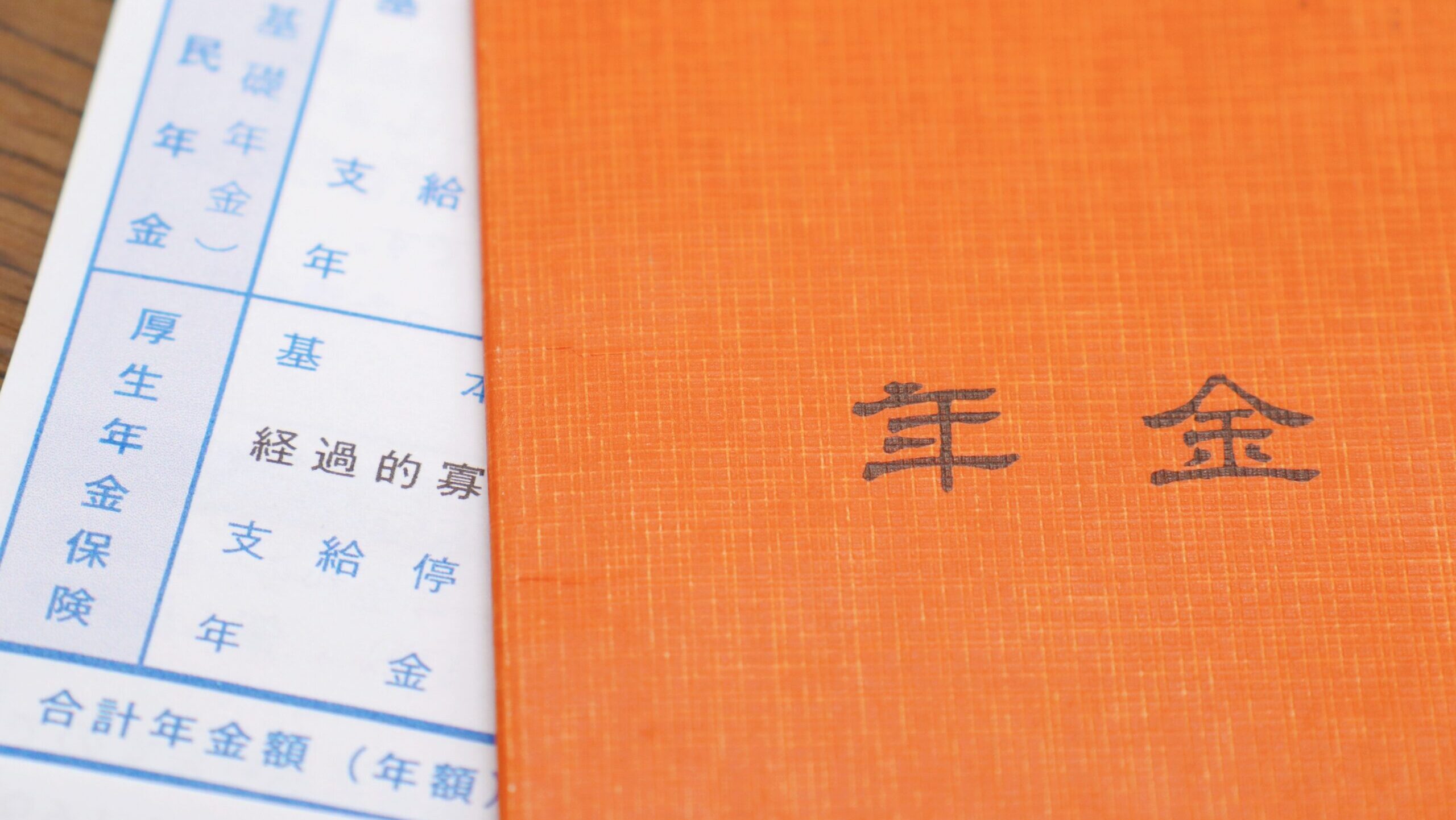令和7年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が国会で成立しました。この法改正により、令和8年(2026年)4月から在職老齢年金の支給停止調整額が現行の50万円から62万円に引き上げられる見通しです。
SATO社労士法人の無料メルマガ
- 面倒な法改正の情報収集は不要!
- 最新の法改正情報の他、労務管理ノウハウや実務対応をわかりやすくお届け
- 経営者・人事担当者向けの無料ウェビナーご招待
在職老齢年金の支給停止調整額とは?
在職老齢年金制度とは、70歳未満の方が厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給する場合、給与や賞与(報酬)と厚生年金の合計額が一定の基準額を超えると、その超過分に応じて年金が一部または全部停止される制度です。
この基準となる金額が「支給停止調整額」と呼ばれます。
- 令和6年度(2024年度):50万円
- 令和7年度(2025年度):51万円
例えば、月の報酬(ボーナスを含めた12分の1)が38万円、年金月額15万円の方であれば、合計53万円となり、支給停止調整額の51万円(2025年度)を2万円超過します。この場合、超過分の半額=1万円が支給停止されます。
この仕組みは、一定以上の報酬がある高齢者には、年金制度の受給者としてだけでなく、年金制度を支える側として保険料を負担してもらうことで、年金制度を維持するという目的があります。
令和8年から支給停止調整額が62万円に見直し・引き上げ
法改正により、令和8年4月から在職老齢年金の支給停止調整額が62万円に引き上げられる見通しです。
ただし、この「62万円」という金額は令和6年度の賃金水準を基にした金額であるため、実際の令和8年度の支給停止額は、賃金や物価の変動を踏まえて最終的に調整されます。
背景にある社会的変化
この改正の背景には、少子高齢化による以下のような要因があります。
- 高齢者の就労意欲の高まり(健康寿命の延伸)
- 企業側の人材確保・技能継承ニーズ
- 在職老齢年金が就労抑制要因になっている現状
厚労省の調査では、65~69歳の方のうち3割以上が「年金額が減らないよう勤務時間を調整している」という結果もあり、在職老齢年金の制度が高齢者の働き方に影響を与えています。
このような背景から、今後は「働いても年金があまり減らない仕組み」を整えることが求められています。
企業側の対応
今回の改正により、以下の点について、企業の人事・労務担当者は注意が必要です。
まず、高齢者雇用制度の見直しです。これまで「年金減額を避けたい」という理由で就労時間を抑えていた高齢者がいる場合には、フルタイム勤務の選択肢を改めて提示するなどの対応が考えられます。また、フルタイムへの復帰等によって、高齢者の報酬が増える可能性があるため、人件費の影響など、早めに検討しておくことが重要です。
制度改正の情報提供も必要です。在職老齢年金の制度は複雑です。そのため、情報の提供と丁寧な説明が求められます。特に、65歳以上で就労継続している従業員への説明は、労使トラブル防止の観点からも重要です。
まとめ
令和8年4月から実施予定の在職老齢年金制度の見直しにより、支給停止調整額が62万円に引き上げられ、高齢者が「働きながら年金をもらいやすい」制度へと転換が図られます。
この改正は、就労高齢者の増加や企業における人手不足対応、高齢従業員の活用といった課題に向き合ううえで、極めて重要な意味を持つものです。
企業の人事・労務担当者としては、改正内容を正しく把握し、高齢者雇用の方針や人事制度に反映する準備を、令和7年度中に進めておくことが求められます。
SATO社労士法人の無料メルマガ
- 面倒な法改正の情報収集は不要!
- 最新の法改正情報の他、労務管理ノウハウや実務対応をわかりやすくお届け
- 経営者・人事担当者向けの無料ウェビナーご招待