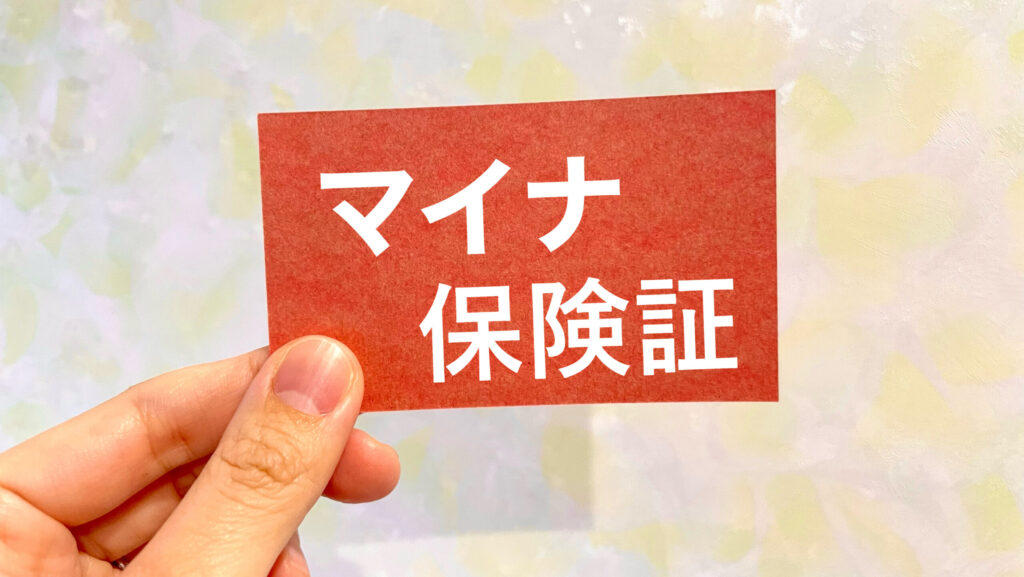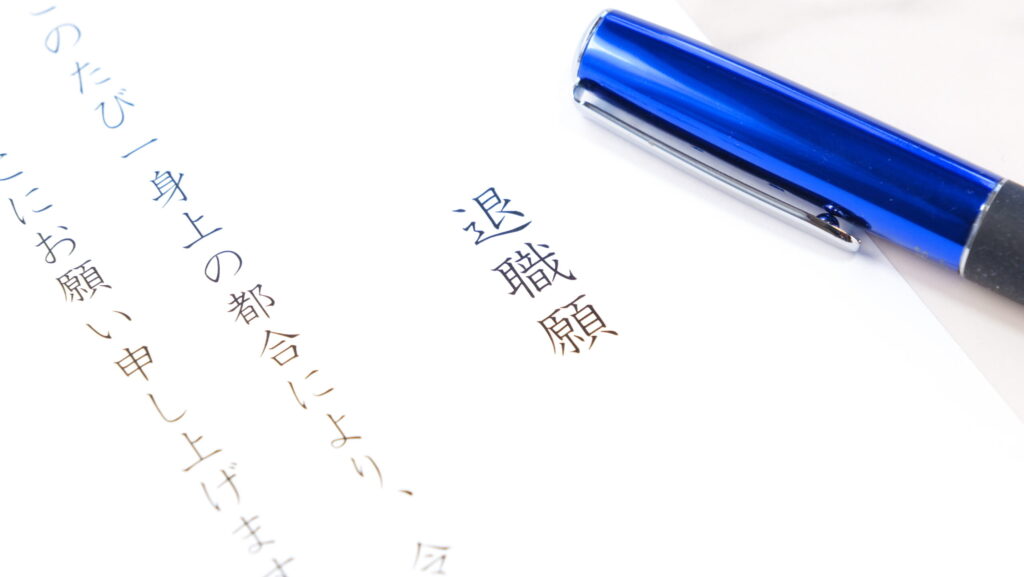労務管理– category –
-

男性従業員の育児休業(育休)期間の平均はどのくらい?
近年、男性社員の育児休業取得を後押しする制度改正が相次いでおり、企業としても「自社の男性育休取得状況は業界・全国平均と比べてどうか」を把握したいという関心が高まっています。 本記事では、まず制度の基本を押さえたうえで、「男性の育児休業取得... -

株式報酬やストックオプションは賃金に該当しますか?
近年、上場企業だけでなくスタートアップや中堅企業においても、従業員や役員に株式報酬を付与するケースが増えています。従業員のモチベーションやエンゲージメントの向上、将来的な企業価値の増大などが主な目的です。 しかし、株式報酬を導入する際には... -

協会けんぽ、マイナ保険証の期限切れにも資格確認書を送付
協会けんぽは、マイナ保険証の有効期限が切れた被保険者に対しても、資格確認書を送付する方針を公表しました。(協会けんぽHP:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-8/7081501/) ご存知のとおり、2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行されな... -

個人事業主や役員の業務災害に労働者死傷病報告が必要になる見通し
2025年7月25日、厚生労働省は「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」について、パブリックコメントを公表しました。今回の改正案では、これまで労働者死傷病報告の対象外だった「個人事業主」や「中小企業の役員等」も、報告の対象として含まれる見通... -

育児休業中に従業員が退職したら育児休業給付金はどうなる?
育児休業中の従業員に対して支給される「育児休業給付金」は、従業員の育児休業取得とその後の職場復帰を支援し、育児と仕事の両立を促進する重要な制度です。 しかし、実際の現場では「従業員が育休中に退職を予定している」「育休取得後に従業員から退職... -

育児時短就業給付金とは?育児のための時短勤務の支援制度
2025年4月から新たにスタートした「育児時短就業給付金」制度をご存じでしょうか? 少子化対策や働き方改革が求められる今、企業には仕事と育児の両立支援がこれまで以上に求められています。この制度は、2歳未満の子を育てながら短時間勤務で働く従業員に... -

【令和7年版】男性社員が育休を取得できる期間
近年、男性の育児参加を支援する制度が整備され、育児休業の取得がしやすくなっています。とりわけ2022年の法改正により、男性社員が柔軟に育児休業を取得できるようになり、企業側にも対応が求められるようになりました。本記事では、令和7年(2025年)時... -

半育休とは?在宅勤務やテレワークは対象?
近年、子育てと仕事の両立を支援する制度が注目される中で、「半育休」という言葉を耳にした担当者の方も多いかと思います。特に、育児休業を取得しながらも一部業務に関わりたいと考える従業員にとって、この「半育休」は重要な選択肢となりつつあります... -

事実婚における子どもの扶養追加手続きの留意点
近年、価値観の多様化に伴い、法律上の婚姻届を提出しない「事実婚」の形を選ぶ家庭も増えてきています。事実婚は、法的な婚姻手続きを行っていないものの、実質的に夫婦として共同生活を営んでいる関係のことをいいます。 企業の人事担当者様においては、... -

執行役員が労基法上の管理監督者に該当すると判断された事例
企業の管理職の中でも「執行役員」が労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうかは、実務でもしばしば論点となる重要なテーマです。 今回は、静岡地方裁判所が令和6年10月31日に下した判決を通じて、執行役員の「管理監督者性」が具体的にどう判断さ...