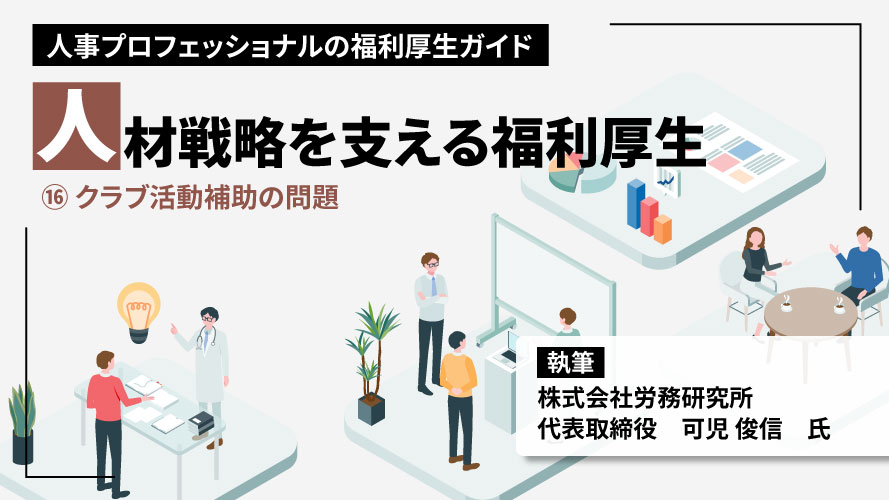可児先生
可児先生「人事プロフェッショナルの福利厚生ガイド」の第16回です。
福利厚生を、人材戦略を支える施策と位置づけ、経営の視点から福利厚生を見直し活用しようという連載です。



私は、福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社、
株式会社労務研究所の代表取締役、可児俊信です。



私がお相手をつとめますサトです。
今日もよろしくお願いいたします。



先生、今日は「クラブ活動」に関するお悩み相談が来てますよ。



どういった内容でしょうか。



「会社が公認しているクラブ活動に対して、部員数に応じた補助金を出して活動を支援しています。社内のコミュニケーションの活性化が目的ですが、一部のクラブ員の飲食に使われていることも目立ち公平性の点で困っています。」……とのことです。



ふむふむ、なるほど。
では今回は、クラブ活動に関しての課題や課題の解決策を解説していきましょう。
課題が多いクラブ活動支援
クラブ活動に関する人事・総務の課題は、いろいろです。まず、クラブ活動の部員となる従業員が少ないこと、2つ目はクラブ活動補助の使われ方の公平性です。3つ目は部員数に応じて会社が補助を出すと幽霊部員が発生しがちなこと。これは公平性の問題でもあります。そして最後に、人事・総務が行っている部費予算管理の事務・手間です。
特に、「公平性」の問題は根深く、それぞれのクラブ活動の内容の差によって、補助金が一部のクラブに偏っていたり、実際活動していないクラブにも予算が配分されているといったケースも見られます。結果として、実際に熱心に活動しているクラブや、その恩恵を受ける社員から不満の声が上がることもあります。
運営委員会がクラブ活動運営を自主管理



クラブ活動への補助はどのような仕組みで運営されていますか?



一つ事例を紹介します。
この会社は従業員数8,000名くらいで、クラブは50以上あります。さらには、スポーツ系クラブだけでなく、文化系や余暇系も幅広く認めています。コミュニケーションの活性化が目的なので,限定していません。部員は最低で10名と下限を設けています。OBの参加を認めていますが、OB人数分への会社からの補助はありません。そして毎年度クラブ員名簿を提出させています。
この会社のクラブは、従業員が負担する部費と会社からの補助金で運営しています。会社は部費を給与控除する手間をかけています。そして部員数に応じた補助金も出しています。



しっかり支援していて、
お金もかなりかけていますね。
この会社のクラブ活動支援の特徴として、各クラブの代表で構成されるクラブ運営委員会があります。各クラブの予算の承認や管理は委員会が自主的に行っており、人事・総務はそのチェックだけで直接予算管理はしていません。クラブは年度始に活動計画書を委員会に提出し、それに基づいて会社に補助金を申請します。同時に部費の徴収も会社に依頼します。年度末に活動実績を提出し、補助金が適正に使用されたていることを報告します。
部費と会社補助金が連動



予算内容はどうなっていますか?
請求できる費用も限られています。消耗品はだめです。懇親会費用も含まれていません。他の会社のクラブ活動は懇親会代が大きな使い途として問題になっていますが、ここでは排除されています。
クラブ活動はコミュニケーション目的ですが、懇親会には補助をしないという考え方です。コミュニケーションが目的だからといって、懇親会も必要とはとらえていませんので、他社のクラブ活動と比べて厳しめです。
クラブ設立申請の際には活動実績や計画を求めています。会社からの補助を狙ったクラブは排除したいのでしょう。クラブの廃止要件もしっかり定められています。私的なコミュニティにならないよう10人未満では存続できないということです。



会社補助金の額はどうなっていますか?
会社補助金の額は部費の2倍以内です。部員数に応じて補助をするのではなく、部費の額に連動しています。幽霊部員がいても、部費が払われていない限り、会社の補助金は増えない仕組みです。
この事例のやり方なら、冒頭にあげたクラブ活動の課題をいくつかクリアできます。



みなさん、参考にしてみてください。
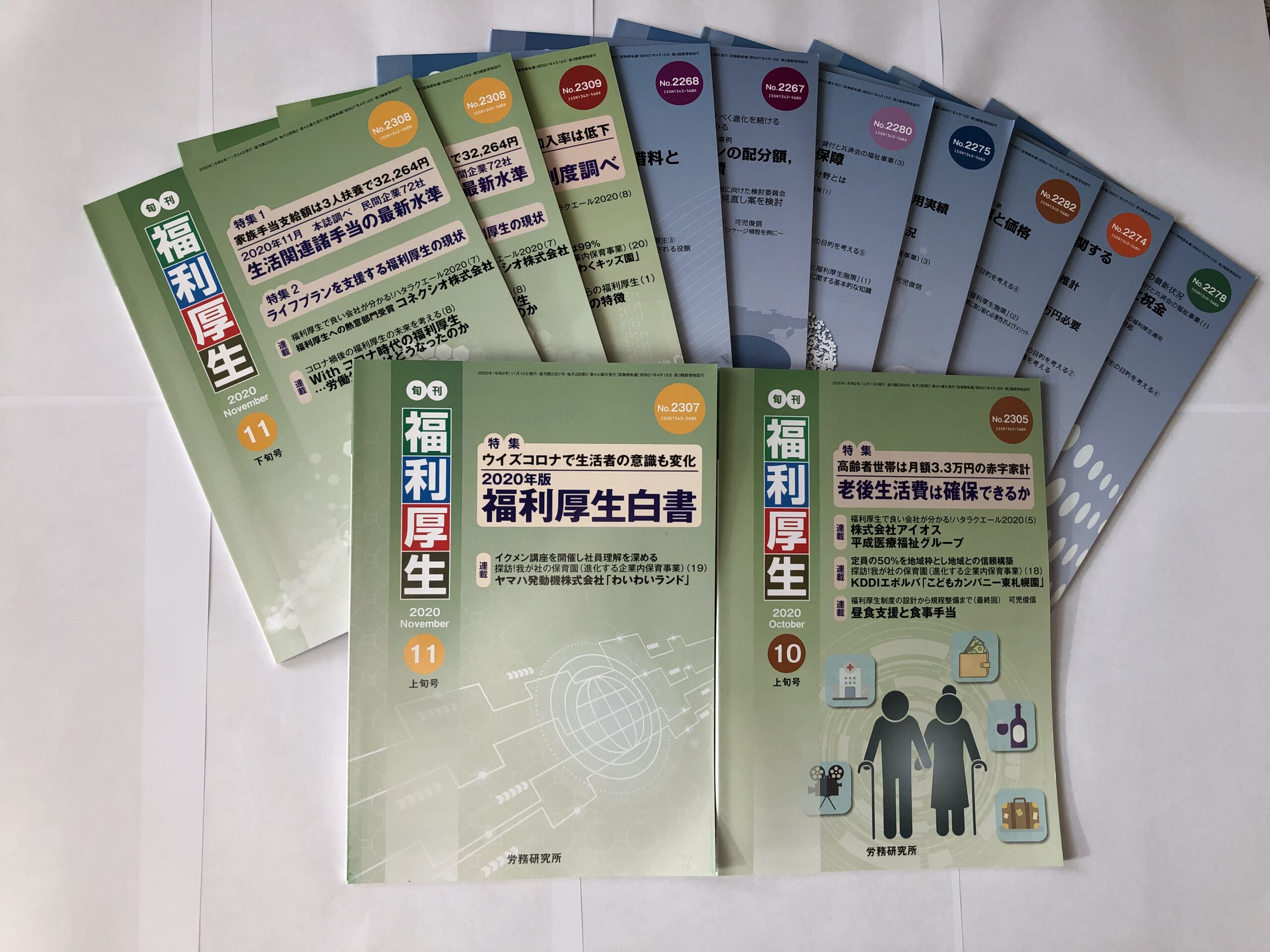
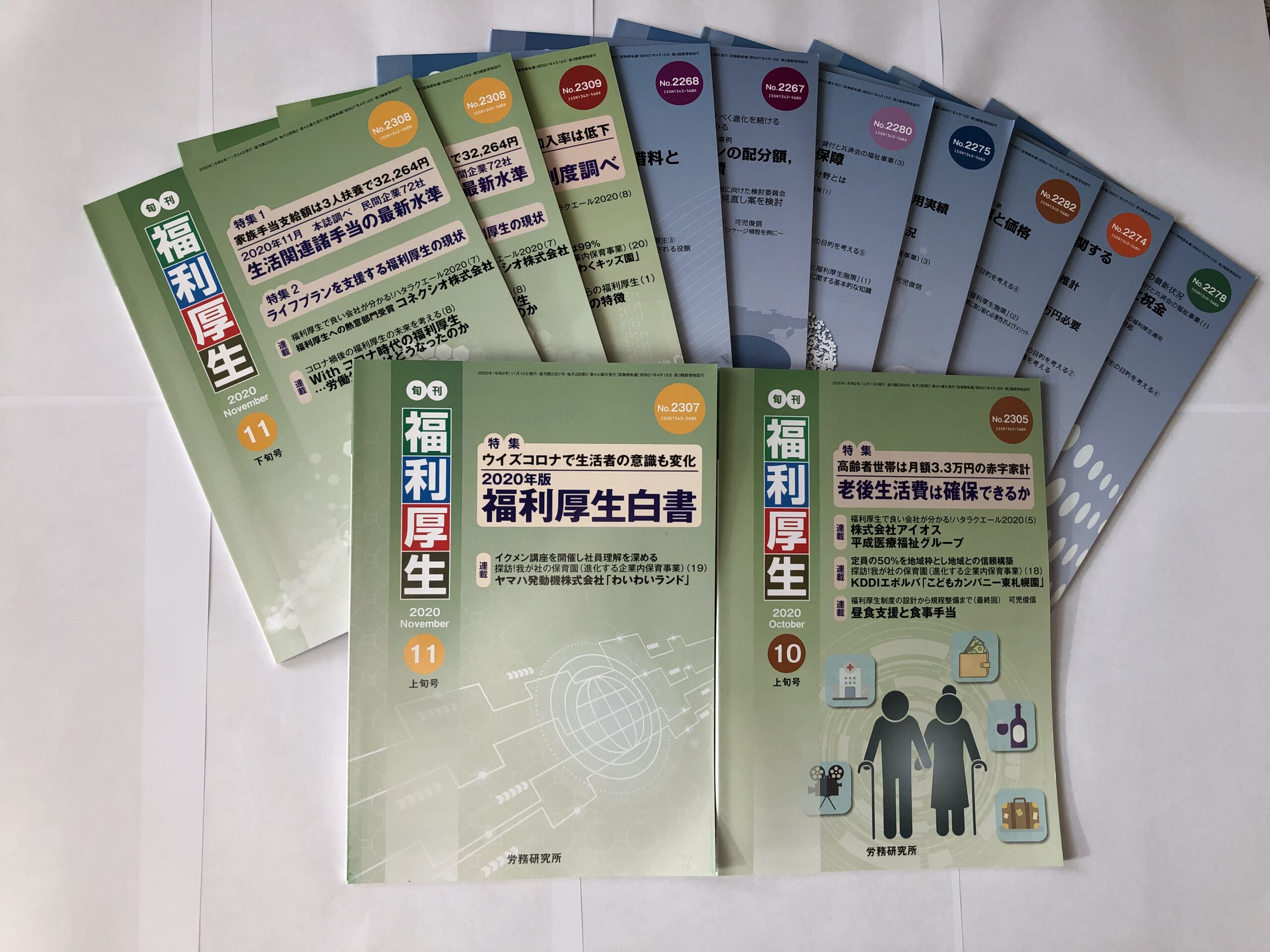
.gif)
.gif)
発行:株式会社労務研究所
株式会社労務研究所では、福利厚生に関する実務誌「旬刊福利厚生」を毎月2回刊行しています。
福利厚生施策の実態調査、事例紹介、動向の解説および重要な関係情報を分かりやすく編集した実務誌です。


株式会社労務研究所 代表取締役
~福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社
千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科 教授
可児 俊信 氏
公式HP:https://rouken.com
ご相談・お問合せはこちらから
1996年より福利厚生・企業年金の啓発・普及・調査および企業・官公庁の福利厚生のコンサルティングにかかわる。年間延べ700団体を訪問し、現状把握と実例収集に努め、福利厚生と企業年金の見直し提案を行う。著書、寄稿、講演多数。
◎略歴
1983年 東京大学卒業
1983年 明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険)
1988年 エクイタブル生命(米国ニューヨーク州)
1991年 明治生命フィナンシュアランス研究所(現明治安田生活福祉研究所)
2005年 千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科教授 現在に至る
2006年 ㈱ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所所長 現在に至る
2018年 ㈱労務研究所 代表取締役 現在に至る
◎著書
「新しい!日本の福利厚生」労務研究所(2019年)、「実践!福利厚生改革」日本法令(2018年)、「確定拠出年金の活用と企業年金制度の見直し」日本法令(2016年)、「共済会の実践的グランドデザイン」労務研究所(2016年)、「実学としてのパーソナルファイナンス」(共著)中央経済社(2013年)、「福利厚生アウトソーシングの理論と活用」労務研究所(2011年)、「保険進化と保険事業」(共著)慶應義塾大学出版会(2006年)、「あなたのマネープランニング」(共著)ダイヤモンド社(1994年)、「賢い女はこう生きる」(共著)ダイヤモンド社(1993年)、「元気の出る生活設計」(共著)ダイヤモンド社(1991年)